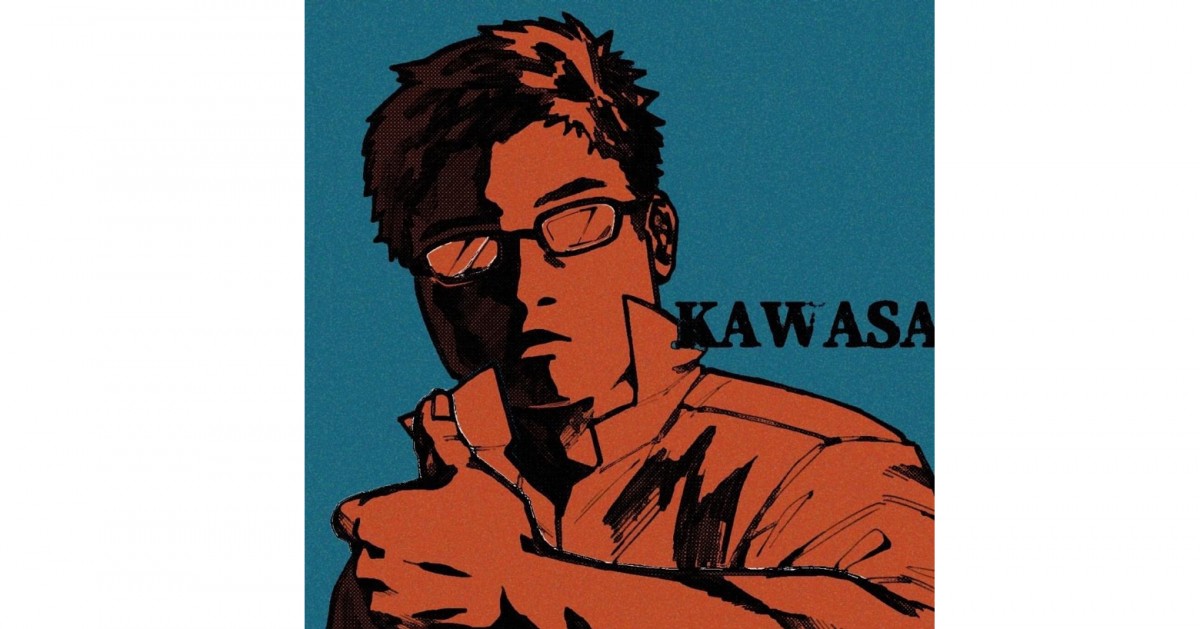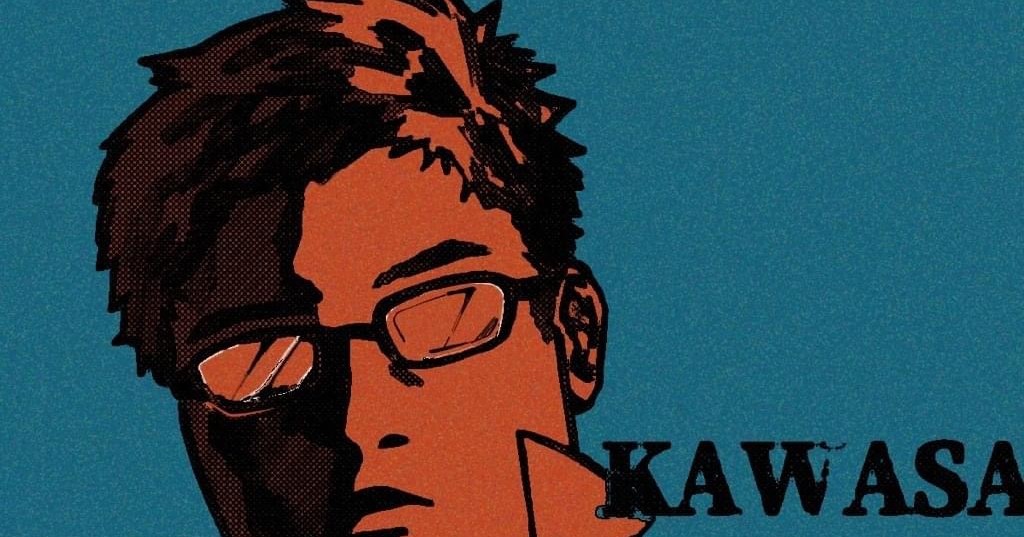「見る」はどれだけ「学び」に関係する?―眼鏡店から始まった私の探求(自己紹介その②奥村智人)
経歴:奥村智人(おくむらともひと):大阪医科薬科大学の小児高次脳機能研究所・LDセンターに勤務し、子どもたちの「見る力」の評価やトレーニングをしています。オプトメトリスト、眼鏡作製技能士、公認心理師の資格を持っています。米国パシフィック大学でオプトメトリー修士課程と教育学修士課程を修了後、大阪医科薬科大学大学院で博士課程を修了しました。*このレターの内容は個人的見解であり、所属と関係はありません。

視覚の研究と実践をはじめたきっかけ
私の視覚分野への探求は、家業である眼鏡店から始まりました。実家で父と母が眼鏡店を経営していたため、その背中を見て育った私は自然とこの分野に興味を持つようになりました。大学卒業後、名古屋のキクチ眼鏡専門学校で基礎的な知識と技術を学び、さらに知識を深めるためにアメリカへ留学しました。当初の目的は、アメリカで眼鏡店経営に必要な高いレベルの知識と技術を身につけ、実家の業務に役立てることでした。
しかし、留学先で目の当たりにしたのは、予想を大きく超える新たな世界でした。アメリカのオプトメトリー分野では、視力だけでなく、両目のチームワークや動体視力に関わる目の動きなど「見る力」全般を扱い、さらに脳が視覚情報を分析・解釈する能力である視覚認知に関する幅広い研究と実践が行われていました。オプトメトリーとは、視力の矯正だけでなく、視機能全般や視覚認知に基づいて、目と脳の働きも含め視覚を総合的にサポートする専門分野です。アメリカをはじめとする多くの国では、オプトメトリストと呼ばれる国家資格が確立されており、眼鏡やコンタクトレンズの処方だけでなく、ビジョントレーニングや様々な目の機能の管理を行っています。しかし、日本ではオプトメトリーが公的な資格として確立されておらず、主に眼科医療がビジョンケアを担っています。
発達障害や高次脳機能障害の分野では、視力以上に視機能や視覚認知が重要な役割を果たしています。また、視機能を評価するための多様な検査方法や、ビジョントレーニングを通じた具体的なアプローチがあり、日々進化しています。日本の眼鏡業界との違いを知ることで、ビジョンケアにおける新たな可能性を探りたいという思いが強まりました。

「見る」を支えるということ
アメリカのオプトメトリストが行う「Behavioral Optometry(行動に着目した視機能へのアプローチ)」の実践は、私にとって新鮮で魅力的でした。学びにくさや生活で何らかの困難がある人に対して検査とトレーニングを提供しているオプトメトリスト、その効果を感じて感謝する患者さんの姿があり、日本のビジョンケアとの違いを痛感しました。日本では視力が基準となる検査が一般的であり、視機能や視覚認知に基づいたサポートは現在でも行われることは少ないです。このような違いを知るにつれ、私は「視覚の専門性を深めたい」と強く思うようになりました。
当初の目的からは大きく脱線し、気がつけば眼鏡に関係するオプトメトリー修士課程だけでなく、教育学修士課程で学びながらビジョントレーニングの研修を受け、日本ではレアな分野の実践と研究の道へと進むことになりました。そして、帰国後、縁あって大阪医科大学(現、大阪医科薬科大学)LDセンターでビジョントレーニングを実践する機会をいただき、その後同大学大学院にて博士課程を修了、現在は小児高次脳機能研究所・LDセンターに所属し、視覚に関する実践と研究を行っています。「アメリカでの経験を生かして日本に戻り、家業を手伝おう」という予定は、すっかり大学での実践と研究にすり替わり、当初とは違う形で「見る」を支える仕事を始めました。

視覚発達支援への取り組み
日本でより良く「見る」を支えるためには何が必要なのか? 見る力の弱さが学習・運動に与える影響に焦点を当てて模索しています。例えば、目をスムーズに動かす能力が十分でない眼球運動が不器用な状態があります。これにより、教科書を読む際に文字を目で追うのが難しくなったり、黒板とノートの間で視線を移動する際に時間がかかったりすることがあります。この眼球運動の不器用さの背景には、視覚情報に注意を向ける視覚的注意という脳機能が関わっていると考えられていますが、そのプロセスの詳細は不明な部分も多くあります。また、視覚認知と言われる「形や位置関係を正しく捉える力」「目から得た情報を脳で処理する力」が弱いと、学習や生活の中で様々な困難を引き起こすことがあります。例えば、漢字の形をうまく捉えることができなかったり、算数・数学の図形を認識できなかったりすることがあります。このような視覚と学習や生活の困難さの関係を解明し、どのようなサポートが有効なのかを探る研究を進めていきたいと思っています。
「実家の眼鏡屋さんにはもう戻らないんですね?」と聞かれることがあります。そのたびに、実家の眼鏡店で両親と一緒に仕事をできなかった(しなかった?)後ろめたさを感じています。それでも、アメリカで出会ったオプトメトリーという新たな学問、そしてそれを活かして誰かの学びや生活を改善できる可能性にやりがいを感じています。視覚に関する研究と実践を続ける中で、日本のビジョンケアに貢献し、眼鏡業界に恩返しができればと思っています。

レターを通して伝えたいこと
今日紹介したように、私はこれまで見るという行為から始まる学びや思考、そしてそれがどのように私たちの成長を支えるのかについて考えてきました。「読みの苦手さは目の動きの問題なの?」「漢字が苦手なのは形が見れてないからなの?」「ビジョントレーニングで学習障害や発達障害はよくなる?」「ビジョントレーニングはスポーツ選手もやったほうがいい?」など、様々な目に関する質問を受けることがあります。レターを通して、視機能や視覚認知の分野での研究や実践に関すること、認知や発達に関することについて、日々の気づきや身近な視点からわかりやすくお伝えしていきたいと思います。
お勧めの図書
ディスレクシア・ディスグラフィアの理解と支援: 読み書き困難のある子どもへの対応
川﨑 聡大 (著)
読み書きに困難を抱える子どもたちに対する支援の本質を深く掘り下げた一冊です。本書は、単なる「How to」に留まらず、ディスレクシア(読みの困難)とディスグラフィア(書きの困難)への真の理解を通じて、子ども一人ひとりの特性を的確に把握し、評価と支援を構築することの重要性を伝えています。支援者が固定観念にとらわれず、子どもの背景やニーズ合わせた支援を学べる内容で、教育現場や支援者の羅針盤となる一冊です。
~3人の井戸端会議~
川崎: ビジョンセラピーが支援学校や療育の現場で流行していると思いますが、その点についてどう思いますか?過度な活用に私は少し疑問を感じています。
奥村: 確かにビジョンセラピーは一定の注目を集めています。私がアメリカで学んだビジョンセラピーと、日本で発達障害や学習障害を対象に行われている"ビジョントレーニング”の実践はかなり異なっていると感じています。海外では、検査に基づいて、視機能や視覚認知の弱さなど明確な機能の問題の改善を目指す手段として位置付けられており、学習や発達の問題への直接的なアプローチとは考えられていません。
川崎: なるほど、日本ではビジョントレーニングをやること自体が目的になってしまっているかもしれませんね。それでは、誤った活用をしてしまう危険性について、もう少し詳しく教えてください。
奥村: ビジョントレーニングに限らず、問題は多くの場合、支援者が知っているある特定の方法や手元にある使い慣れた教材、あるいは他の子どもにやってみて効果があった方法や教材を安易に活用する点にあると思います。それぞれの子どもの困難さの背景や状態が違うため、一律の方法では効果的な支援は行えません。ビジョントレーニングを含むあらゆる支援法は、その子どもに合った方法を見極めることが重要です。
荻布: 奥村先生、留学から戻られてから日本のビジョンケアの現状についてはどのように感じてますか?
奥村: 眼鏡作製技能士の国家検定化など、日本でのビジョンケアは進歩している部分もありますが、まだまだ課題が多いと感じています。眼科医師、視能訓練士、眼鏡作製技能士がいても、発達障害や高次脳機能障害の視覚の問題に対応できる人がいないのが一番大きな問題だと思います。そういった中で、ビジョントレーニングが行われているけれど、それぞれが考えるビジョントレーニングの概念や方法が統一されていないのが現状です。本当の意味で、見ることの大切さやビジョントレーニングの実践が全国的に広がっているとは言い難いです。これらの課題に向けて取り組んでいきたいです。
荻布: これからのレターで特に取り組みたいテーマや、伝えていきたいポイントがあれば教えてください。
奥村: 視機能の問題がどのように日常生活や学習に影響を与えるかを理解してもらいたいです。一方で先ほど川﨑先生の質問にもあったように、必要な人に適切な支援が届くようにできるだけ正しい情報を伝えていきたいですね。誰にでも効果がある魔法の支援はありません。私自身まだまだわからないことがたくさんあるので、一緒に学んでいければと思います。
次回は「“障害かどうか” は支援を始めるためにそれほど重要なことなのか? (自己紹介その③荻布優子)」です。おたのしみに。
すでに登録済みの方は こちら