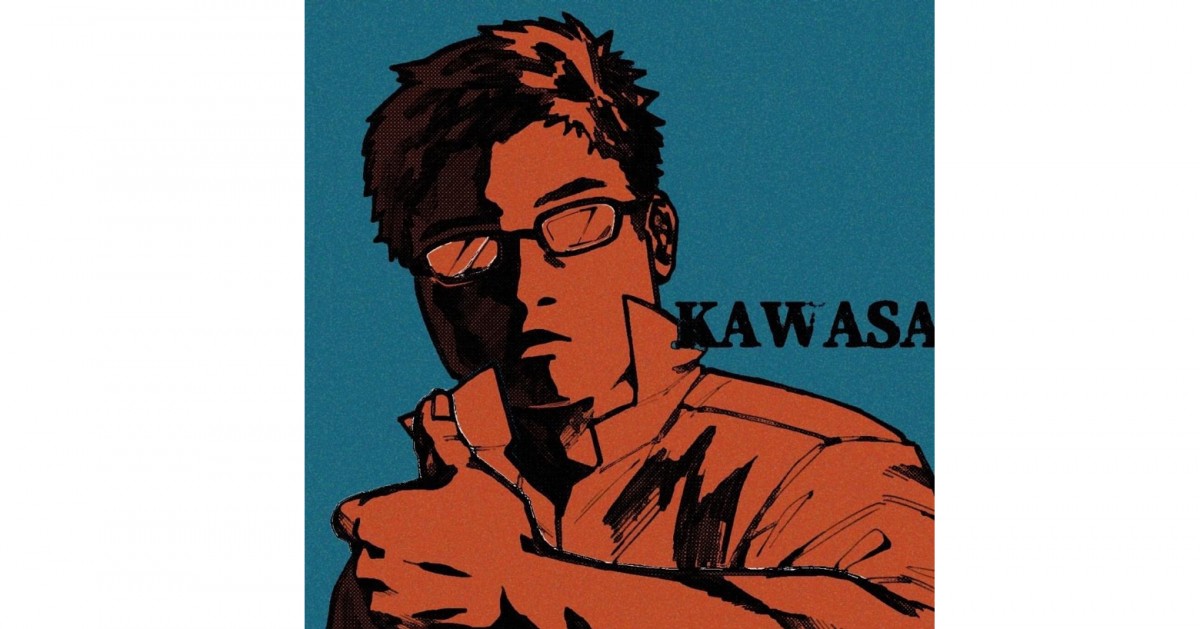誤解だらけの「算数障害」 理解編(前編)―多様なつまずきと、支援を妨げる言葉の危うさ―
「九九の定着」「文章題の理解」「計算ミス」─学校で目につきやすい算数のつまずきに対し、いまだに「努力不足」か「障害」かという極端な解釈が横行しています。しかし実際には、読解力や実行機能、語彙力といった多面的な要因が複雑に絡み合い、心理社会的要因も加味して学習は成り立っており「苦手さ」はその結果として現れたものと理解する必要があります。本稿では、診断名に飛びつく前に知っておきたい、学習困難の背景と構造的誤認のリスクを整理し、支援の原点を問い直します。
原因でもあり結果でもある「学習の困難さ」― 短絡的な見立てが本質的な支援を惑わせる ―
「九九が覚えられない」「計算問題になると急に集中が切れる」「文章題が苦手で式が立てられない」―こういった算数の苦手さに関する相談は、決して珍しいものではありません。むしろ、小学校の学習場面において「よく見かける状態」と言えるでしょう。しかし、その状況に私たちが直面したとき、社会や周囲の大人から返ってくる反応は、しばしば極端な二択に収束します。
〇ひとつは、「努力不足」という価値観による説明。
〇もうひとつは、安易に「算数障害」といった診断名に回収してしまう立場です。
そしてそこに共通しているのが、複雑な現実を単純な原因に還元してしまう思考の危うさ、すなわち極端な還元主義的発想です。
けれども、本当にそれでいいのでしょうか。もちろんよろしくありません。極端な還元主義的発想によって安心するのは、それを信じたい周囲の大人だけであり、子どもの本当に困り感の背景を見落とすきっかけになりかねません。
実際、学習面のつまずきは、子どもにとってのさまざまな困難の「原因」であると同時に、「結果」として表面化する現象であると捉えた方がいいでしょう。たとえば文部科学省の「不登校児童生徒調査」(2023年)では、学業不振や授業理解の困難さが継続的な学校回避行動の引き金になる可能性が指摘されています【1】。また、国立教育政策研究所の分析でも、学習困難が学校回避行動の一因となり得ることが繰り返し報告されています【2】。これは「勉強ができないから不登校になる」といった短絡的な理解に繋げるものではありません。むしろ、学習上の困難は、子どもの内的状態や周囲との関係性を映し出す「鏡」として捉えるべきです。すなわち、子どもの学習は、学校での安心・安全が担保されて初めて成立する営みであり、極論すれば、それを脅かすあらゆる要因が学習のつまずきの「きっかけ」になり得るのです。にもかかわらず、学力の遅れや学習困難が「努力不足」や「家庭の教育の問題」と見なされる社会的風潮はいまだ根強く存在します(この背景には、日本の教育文化に深く根ざした努力至上主義の影響があります)。
学力とは、本人の努力と家庭のしつけの成果であり、できないことはそのどこかに問題がある、といった非科学的かつ文化的に陳腐化した価値観が、限局性学習症に限らず、さまざまな困難を抱える子どもに「説明の余地」を与えにくくしているのです。こうした傾向は、教育社会学や心理学の研究でも繰り返し問題視されています【3】【4】。
また、昨今学習障害への理解が徐々に社会に浸透しつつある一方で、読み書き困難や発達障害の診断がつくような典型的な事例(※ただしそれ自体も決して単純ではありません)に比べ、複数の要因が絡み合う場合や学年が上がった人は「見たいものしか見なくなる」傾向が強まります。こういったことも「なぜできないのか」という問いに他者が真正面から向き合うことがますます難しくなる要因の一つです。包括的な掘り下げを行わないまま、評価や支援が即断的・極端に傾いたとき、本来見えるはずだった子どもの実態が、かえって見えなくなってしまうというリスクが生じます。
本稿では、「算数のつまずき」に潜む多様な背景に光を当て、表面的な診断名や精神論から一歩進んだ、実態に即した支援の可能性を考察していきます。