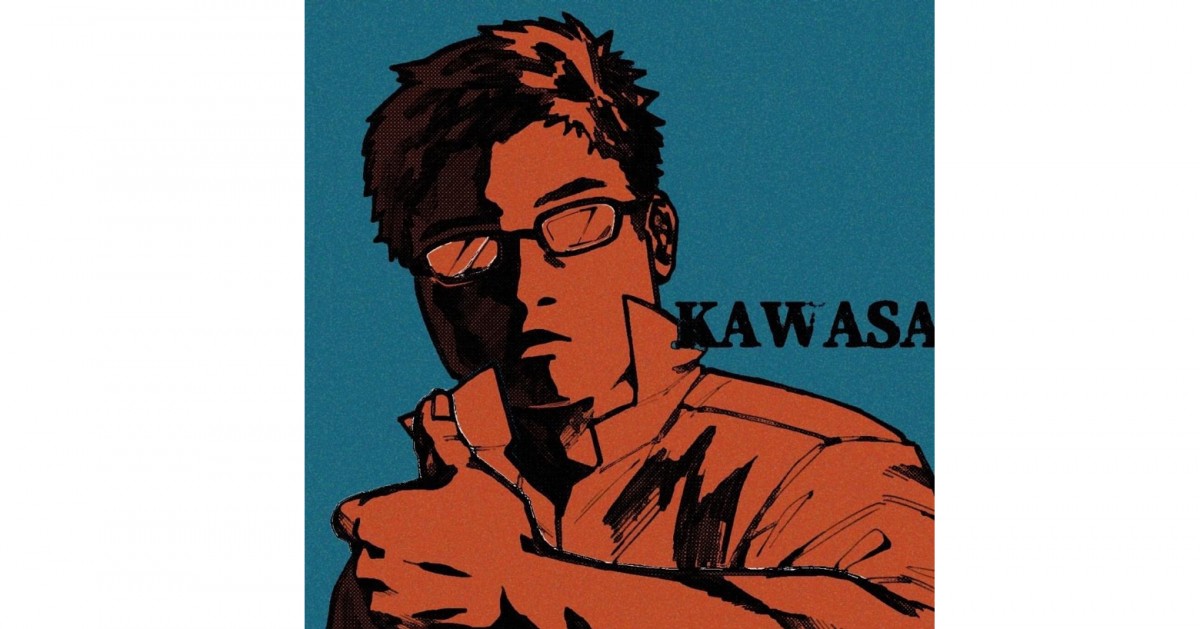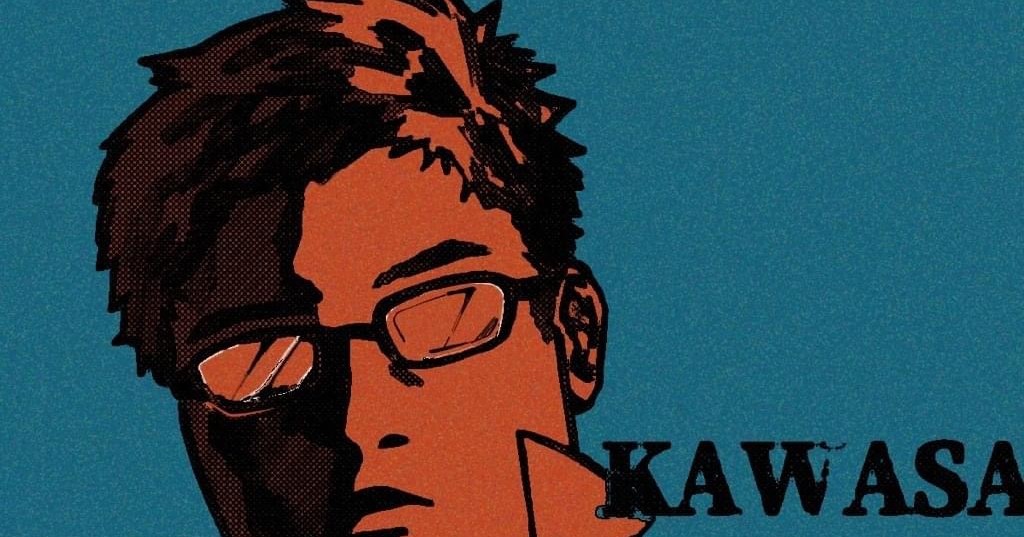世界ダウン症の日(World Down Syndrome Day)後編「それは『余分』ではない」
何が起きたのか? 少したって冷静に振り返る
2025年2月19日、三重大学は『ダウン症候群の人の細胞から余分な21番染色体を除去』というタイトルで、研究成果のプレスリリースを公表しました。発表の内容はゲノム編集技術であるCRISPR-Cas9とDNA修復機構の一時的な抑制(LIG4およびPOLQのsiRNAノックダウン)を組み合わせて、「ヒト21番染色体のトリソミー細胞から1本の染色体を除去する手法を開発した」というものでした。21トリソミーは、言うまでもなくダウン症候群で最も多く見られる染色体構成です。
この発表は、技術的には確かに注目にあたいするものであった一方で、発表直後からさまざまな立場からの批判や懸念の声が相次ぎました。特に問題となったのは、プレスリリースの中で「出生前診断を踏まえた出産の是非に関する議論に、『治療する』という新たな選択肢を提示する可能性を秘めています」と書かれていた点です。これは、「ダウン症のある胎児は『治療』されるべき存在」という印象を与えかねず、ダウン症のある人々の尊厳や生まれてくる命の意味に関わる、重大な社会的メッセージを含んでいると受け取られました。
2月21日には日本ダウン症協会が公式声明を発表し、この表現について「ダウン症のある人の存在を否定するものに聞こえる」として、強い懸念を表明しました。その後も、遺伝医療、倫理学、当事者団体、メディアなど、さまざまな方面から批判や疑問の声が寄せられました。議論は研究内容の技術的な妥当性だけにとどまらず、大学の広報姿勢や研究倫理の在り方そのものにまで及んでいきました。
こうした状況を受けて、三重大学は2月27日に修正版のプレスリリースを公開しました。タイトルは『過剰な21番染色体の除去』に変更され、出生前診断との関連を示唆する記述や、一部ステレオタイプ的と批判された表現が削除・修正されました。しかしながら、修正の内容については『表面的な言い換え(例えば「余分」を「過剰」)にとどまり、構造的な問題点は残されたままではないか』という批判も続いています。
このように、今回のケースは一つの研究成果が、単なる技術開発の範囲を超えて、社会的な価値観や命のあり方といった深い問いを投げかける出来事になりました。科学と社会の接点において、どのような言葉で成果を伝えるか、その選択の重みが強く問われたケースと言えます。
*この記事を読む前に必ず「世界ダウン症の日-前編-」の記事を読んでください!
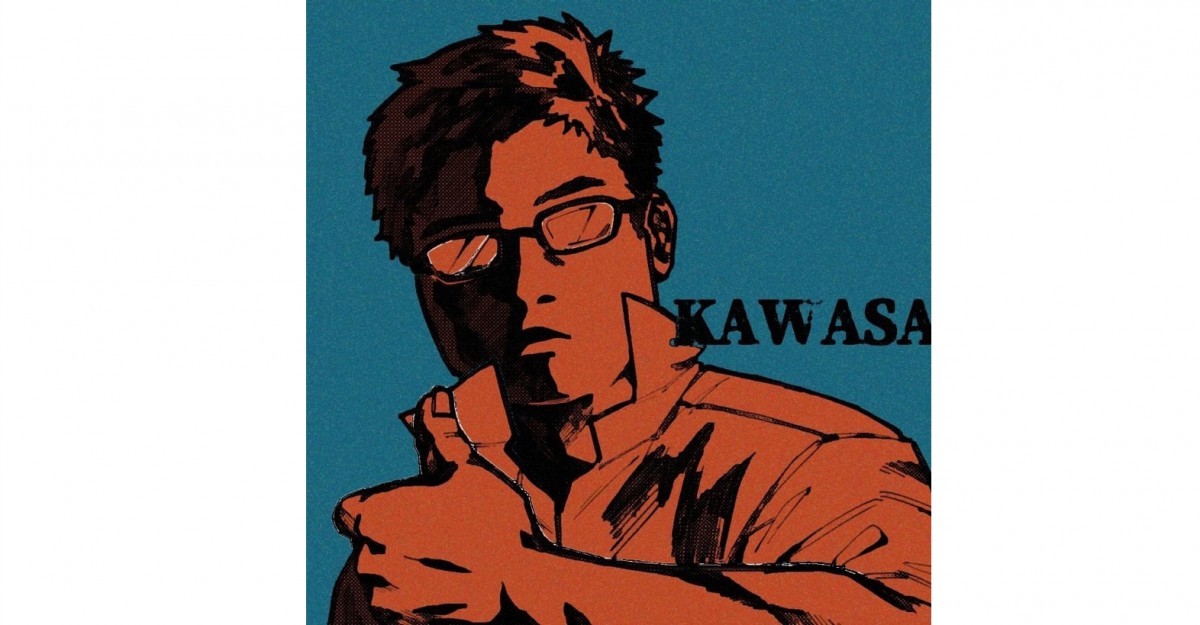
研究独自課題:染色体切断と修復抑制がもたらすリスク
あくまで私はこの領域の専門家ではありませんが、一人の研究者としてこの論文を拝見した際に感じた疑問を、以下に整理してみたいと思います。
まず前提として、染色体除去をはじめとする遺伝子治療の技術は、ドラマやアニメの世界のようにすぐに人に応用できるものではありません。特に染色体単位での操作となると、その技術的・倫理的ハードルは非常に高く、細胞レベルで一時的な成功が見られたとしても、それが実際の治療として現実世界で使われるようになるには、数十年単位の時間と多くの検証が必要になることがほとんどです。
今回の研究の特徴は、ゲノム編集技術「CRISPR-Cas9」を用いて、21番染色体の両端近くを複数のガイドRNA(gRNA)で同時に切断し、さらにDNA修復に関わる遺伝子(LIG4とPOLQ)をsiRNAで一時的に抑えることで、染色体をまるごと除去しようとした点にあります。
CRISPR-Cas9自体は、現在さまざまな遺伝子治療や病態モデルの開発において広く使われており、絶対的に安全とは言えませんが、過去の遺伝子編集技術と比べると、その安全性や安定性は飛躍的に向上しているとされています。その意味では、今回の研究もそうした既存技術の延長線上に位置づけられるものだと思います。ただし、安全性が高まっているとはいえ、決して「簡単にポンと導入できる」ような軽い技術ではないことも、あわせて強調しておく必要があります。テレビドラマの『インハント』でCRISPR-Cas9を題材にしたエピソードが登場したことを思い出される方もいるかもしれません。
このような手法を応用すれば今回のように、染色体除去の成功率を高めることが期待される一方で、いくつかの注意点もあります。たとえば、gRNAを複数使って広範囲を標的にする構造上、意図していない場所にも影響が及ぶ「オフターゲット効果」が起きやすくなるとされます。この影響は設計次第で抑える工夫も可能ですが、評価は慎重に行う必要があります。
また、DNAの修復機構を一時的に弱めることで、目的とする染色体を修復させずに消去しやすくなる一方で、細胞の持つ本来の安定性を損なう可能性も否定はできません。DNA損傷が十分に修復されないまま残ると、細胞にとって有害な変化が蓄積してしまうリスクもあるとされています。
こうした点を踏まえると、今回の研究で特に注目すべきなのは、「実験の評価期間が48時間に限られていた」ということではないかと思います。細胞を扱う実験としては妥当な設定かもしれませんが、オフターゲット効果や修復の不完全性といった影響が、時間の経過とともにどう現れるかについては、長期的な観察が不可欠です。今回の発表では、その点についての検討がまだ十分に行われていない印象を受けます。
そのため、技術的な工夫が凝らされていたことは確かですが、より慎重な安全性の検証が今後は求められるだろうと思われます。そして、こうしたリスクや限界についての情報が、発表当初の段階では十分に共有されていなかったことも含めて、研究者や大学広報には、より丁寧な説明と発信の姿勢が期待されるところです。
私のようにこの領域の専門家でない立場の者でさえ、こうした課題がこれだけ目につくのですから、専門家の目から見ればさらに多くの論点や懸念があるかもしれません。改めて強調したいのは、細胞レベルで一時的に成功したとはいえ、こうした技術が実際に現実世界で使われるようになるまでには、相当な時間と手間がかかるという現実です。そうした前提をふまえて、この研究の意義や位置づけを冷静に受け止めていく必要があると思います。
あ、言うまでもありませんが、もちろん私が本当に考えてほしいと感じているのは「技術的にできるかどうか」ではなく「疾病や特性そのものを除去すべき対象とみなすフレームで語られてしまうこと」の方なのです。これは本当にあってはならない事なんです。