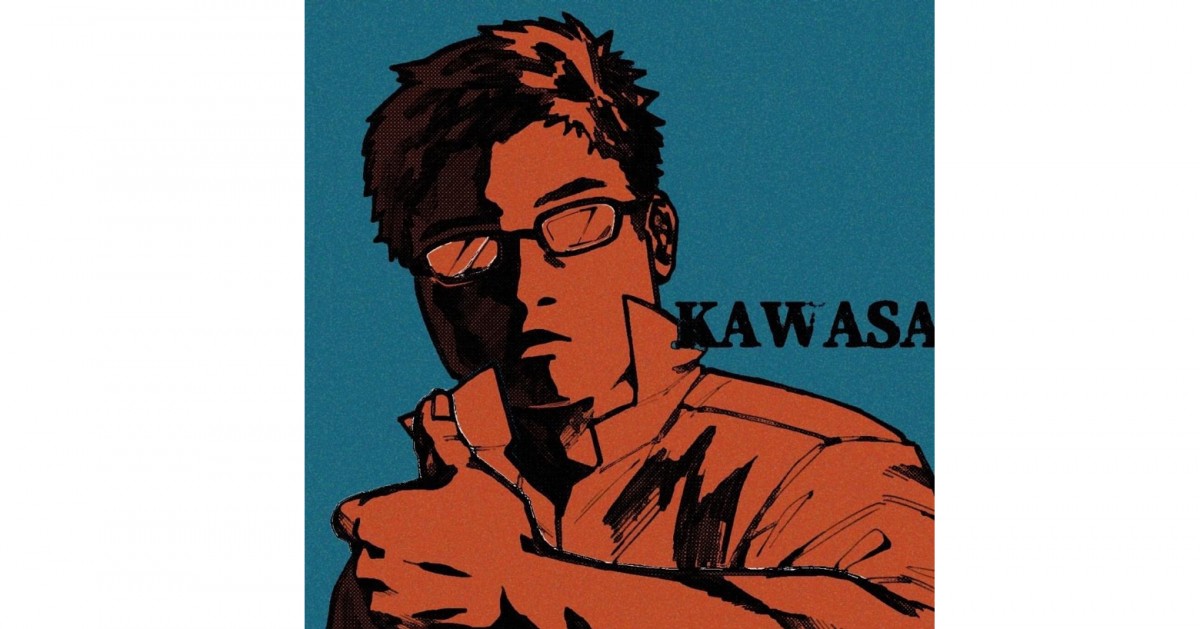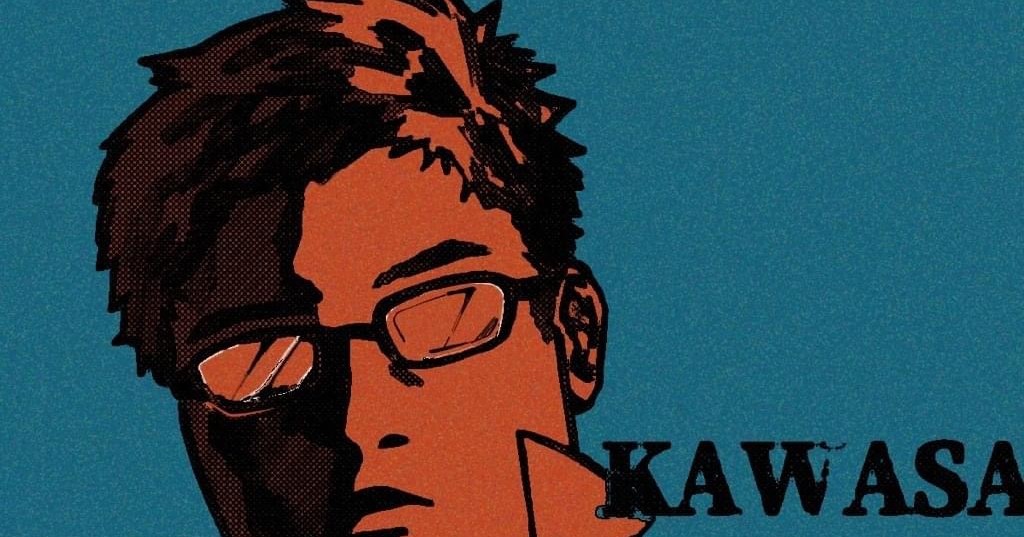なぜ私たちは「知能」に右往左往させられてしまうのか?
3人の先生のニュースレターは、こどもの発達や障害、広く保育や教育に関して気になるニュースや最新の研究を取り上げます。川崎・奥村・荻布のそれぞれの専門性を活かしながら子どもの発達支援や教育・社会福祉のエビデンスを深堀し、経験値をエビデンスとして皆様の生活に還元しようとする試みです。根拠の乏しいハウツーとは一線を画して、間違いの少ない情報を届けたい人に届けていくことを目標にしています。

「知能とは何ですか?」という問いかけをすると、困り顔になってしまう人が多いような気がします。少し聞き方を変えて「知能のイメージは?」と問うと、「頭のよさ…!?」「知能指数…IQが高いとか低いとか…!?」のように最後に疑問視がくっついた答えが聞かれるような。これはある種の仕方のなさがあると私は思っています、なぜなら知能は構成概念であり、具体的に目に見えるものではないからです。
知能とは何か?
知能の歴史を探ると、様々な医者や心理学者が、その人それぞれの考え方を反映した知能の定義を提唱しています。例えばピアジェの認識の発達の文脈のことばを借りるなら「動的な環境と固体の調整機能」となります。またターマンは「抽象的思考をなしうる能力」、ウェクスラーは「目的をもって行動し、合理的に考え、効率的に環境と接する個人の相対的能力」と定義しました。
「知能」はどのようにして測られるのか?
知能検査では、目に見えない構成概念である「知能」を何とか目に見える形にしようとして数値化する試みです。先に説明した通り、知能は様々な定義がありますから、それぞれの定義に合わせて「知能」を測ろうとする知能検査が開発されてきています。大事なところは、検査によって測ろうとしている「知能」のとらえ方は少しずつ異なることと、あくまでも知能検査では人間の能力の“ある側面”を測ろうとしているということです。
では知能を測る場面で、具体的に何をどうしているかというと、パズルやカードを操作してみたり、絵を見て考えて指示に沿って推理したり、ことばのクイズに答えたり、状況や自分の知っていることを説明したり、絵や図形をかいたり…というように、検査者から出された問題にその場で答えていきます。これはどの検査も共通です。検査が変わると、これらの問題の種類(性質)やその組み合わせ方、問題の配置(出題順位や範囲)が異なってきます。これらは経験の有無に左右されにくい、発達の過程のなかで誰もが自然と通過していく・獲得していく力を測っているといわれています。ここでのポイントは「その検査場面で発揮されたパフォーマンス(正答数)」という目に見える行動指標によって、目に見えない「知能」という構成概念を数値化しようとしている、という少々あたまがこんがらがってきそうなことをしている、というところにあります。
主要な知能検査の種類は2つ
いま日本でよく選ばれている個別式(検査者と1対1で取り組むタイプの)知能検査は、田中ビネー知能検査とウェクスラー式知能検査の2種類であると思います。順に紹介します。
まず田中ビネー知能検査は、1947年に出版され、改訂を重ねて現在は2024年に改訂された第6版が最新です。そもそも知能検査は1800年代後半からヨーロッパで開発が進み、Binet,A.とSimon,Tによって完成されたビネーシモン知能尺度がその最初です。1908年には改訂版知能検査が完成され、精神年齢の概念が導入されました。この流れを汲んで、日本におけるより精度の高い尺度として作成されたのが田中ビネー知能検査です。田中ビネー知能検査は、知的障害の有無の鑑別と、検査結果をもとにした日常の課題設定の検討がしやすい、というところに長けています。どちらかといえば特別支援学級や特別支援学校など、知的障害があることが明らかなお子さんによく用いられます。
この検査の一番の特徴は年齢尺度が採用されており、精神年齢が算出されるところです。年齢尺度とは課題の難易度順に問題が配置されており、その正答数から「今現在のできること・わかることはどの程度か?」を年齢で表すものです。一般的に想像される精神的な成熟度のようなものを表している“精神年齢”とは少し意味合いが違います。またこの精神年齢をもとにして、知能指数(IQ,特に比率IQともいわれます)を算出します。これは伝統的な知能指数の計算式である「精神年齢÷生活年齢(生まれてからの年齢)×100」を使います。これは「おなじ年齢の子どもたちと比べて何割くらいのことができていそうか?」を表していると考えるとよいでしょう。ここでの知能指数(IQ)もよくメディアなど…例えばクイズ番組で「これが解けたらIQ▲▲」というのとは違っています(というか「これが解けたらIQ▲▲」は何を根拠にいっているのか全く意味不明…と思っています)。IQが100のとき、年齢相応の発達段階であるという風に読み取ります。
次にウェクスラー式知能検査は、年齢によって3種類の検査があります。2歳6か月歳から7歳3か月まではWIPSSI‐Ⅲ知能検査(ウィプシ・スリー)、5歳から16歳11か月まではWISC-Ⅴ知能検査(ウィスク・ファイブ)、16歳から90歳11か月まではWAIS‐Ⅳ知能検査(ウェイス・フォー)、です。1900年代(ビネー・シモン検査のころ)は知能を一次元の能力としてとらえられていましたが、これは知能が高ければ知的作業に関しては軒並み優れているということになります。それでは説明がつかないケースが存在するため、1930年代ごろからは、知能は様々の能力の総体であるという多角的なとらえ方が提唱されるようになりました。その流れのなかで開発されたのがウェクスラー式知能検査です。