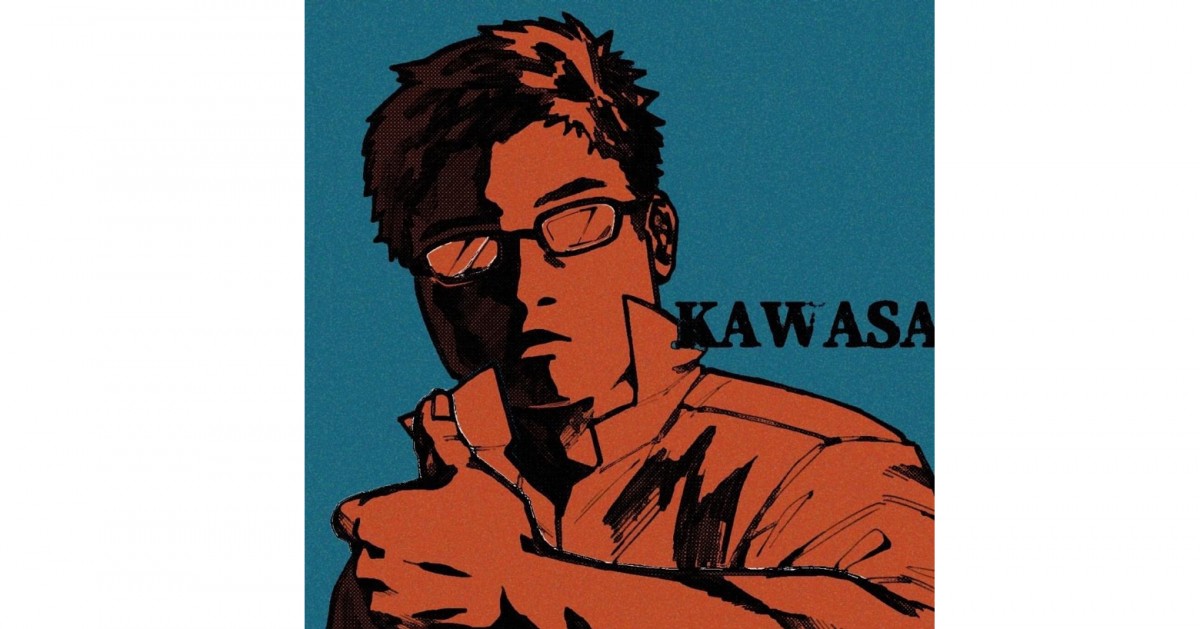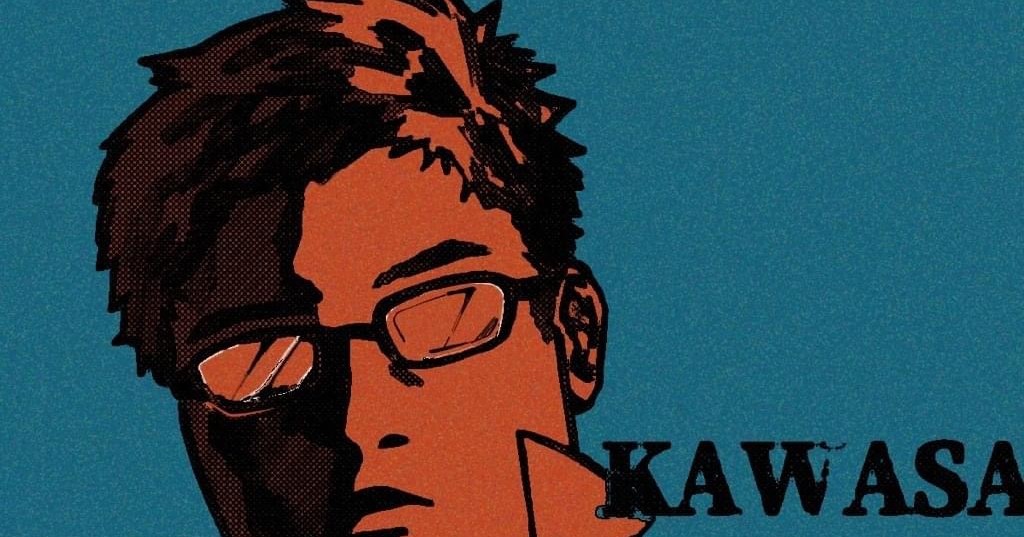宿題の意味はどこにあるのか?学習に困り感のある子どもの宿題問題-その①-
3人の先生のニュースレターは、こどもの発達や障害、広く保育や教育に関して気になるニュースや最新の研究を取り上げます。川崎・奥村・荻布のそれぞれの専門性を活かしながら子どもの発達支援や教育・社会福祉のエビデンスを深堀し、経験値をエビデンスとして皆様の生活に還元しようとする試みです。根拠の乏しいハウツーとは一線を画して、間違いの少ない情報を届けたい人に届けていくことを目標にしています。継続的な執筆のためにぜひサポートメンバー登録もお願いいたします。

宿題とはなにか?を定義してみようと思ったところ…。
わたしたちの育ちの過程を振り返ったとき、「宿題」を一度も経験したことのない人はいないだろうと思います。宿題は多くの人にとって馴染み深いキーワードであり、私の推測の域を出ないもののポジティブな思いでだけで宿題を説明できる人はいないのではないでしょうか。
自分の子ども時代も、また子どもを育てる側にまわっても私たちの頭を悩ませ続ける宿題は、その学術研究は少なく、教育用語としての「宿題」という言葉の定義は見当たりません。というか教育基本法にも学校教育法にも、学習指導要領にも宿題という言葉は出てこないようです。たとえば学習指導要領(2017)に「家庭との連携を図りながら児童の学習習慣が確立するよう配慮しなければならない」 というところが、文部科学省が宿題に言及している唯一のところのようです(宮崎,2022)。
この記事は無料で続きを読めます
- 宿題のメリット/デメリット
- 宿題を教師目線で種類分け…じつは意図がある?
- いわゆる「宿題(反復練習)」を科学してみる
- 宿題とどう向き合うか?
すでに登録された方はこちら