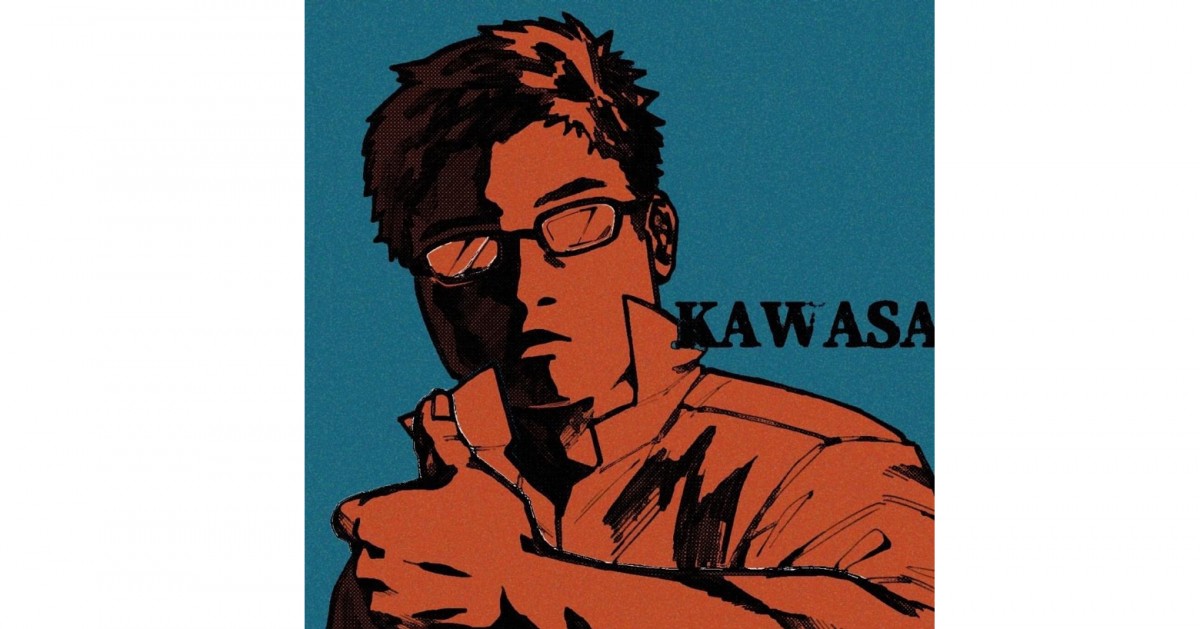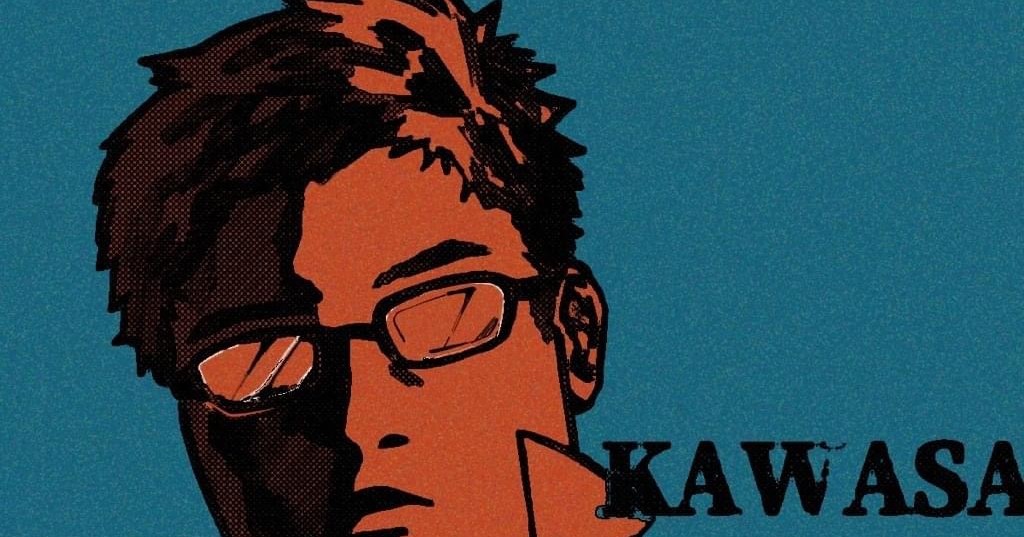自閉スペクトラム症は視覚優位なのか?
今回は「視覚」に注目し、自閉症の人の視覚の特徴やその背景について考えてみます。自閉スペクトラム症は本当に視覚優位なのか? それは多くの人に当てはまるのか? 過去の研究を交えてお伝えします。

【自閉スペクトラム症とは?】
自閉スペクトラム症(ASD:Autism Spectrum Disorder)は、主に社会的なコミュニケーションの難しさや興味や行動の偏りといった特性が見られる発達障害の一つです。「発達障害」という言葉には、いまだにさまざまなイメージや先入観がつきまといますが、ここではあえて「障害」という表現を使いつつ、それが「できる・できない」を単純に示すものではなく、脳の働き方の違いとして理解されつつあることも含めて、お伝えしていきたいと思います。近年、神経多様性(Neurodiversity)という考え方のもと、それぞれの特性を否定せず、多様な感じ方や学び方の存在を尊重する社会づくりが重視されるようになってきました。
【それって誤解? 自閉スペクトラム症の視覚優位】
「自閉症の子はパズルが得意らしい」「一度見ただけの地図を覚えられる子がいる」といった話を耳にすることがあります。一見すると、映画の中の特別な才能を持った登場人物のようにも思えるエピソードです。しかし、最近の研究では、自閉スペクトラム症の人たちが見ることに関して一律に優れた能力を持っているわけではなく、捉え方の違いがあることが分かってきています。例えば、複雑な図形の中から特定の形を探し出す問題(埋め込み図形課題)や見本どおりに模様を作る問題(図形構成課題)では、自閉スペクトラム症の人たちは一般の人より高い成績を示し、細部に注目する力が高い人が多いことが報告されています。一方で、大きな文字(全体像)が小さな文字(細部)の集まりでできているような図を見ると、自閉スペクトラム症では全体像より細部の小さな文字に注目してしまうことが多いです(Happé & Frith, 2006)。例えば、「S」という大きな文字(全体像)が、たくさんの小さな「T」の文字(詳細)で構成されている図を見せたときに、定型発達の人はまず全体像の「S」に目がいきやすいのに対し、自閉スペクトラム症の人は先に詳細の「T」のほうに気づくことが多いといわれています。これは、「木を見て森を見ず」の状態であり、全体像を捉える力が弱い人が多いということです。これらの研究結果は、自閉スペクトラム症の人たちが見ることに関して優れた能力があるいう一括りのイメージではなく、見て捉える際のスタイルが違うという理解が適切であることを示しています。また、複数の研究結果をまとめて分析した調査(メタアナリシス)では、自閉スペクトラム症が得意と言われている視覚課題において、実は得意不得意のばらつきが大きく、すべての人に当てはまるわけではないというのが研究の結論です(Muth et al., 2014)。
別のメタアナリシスでは…