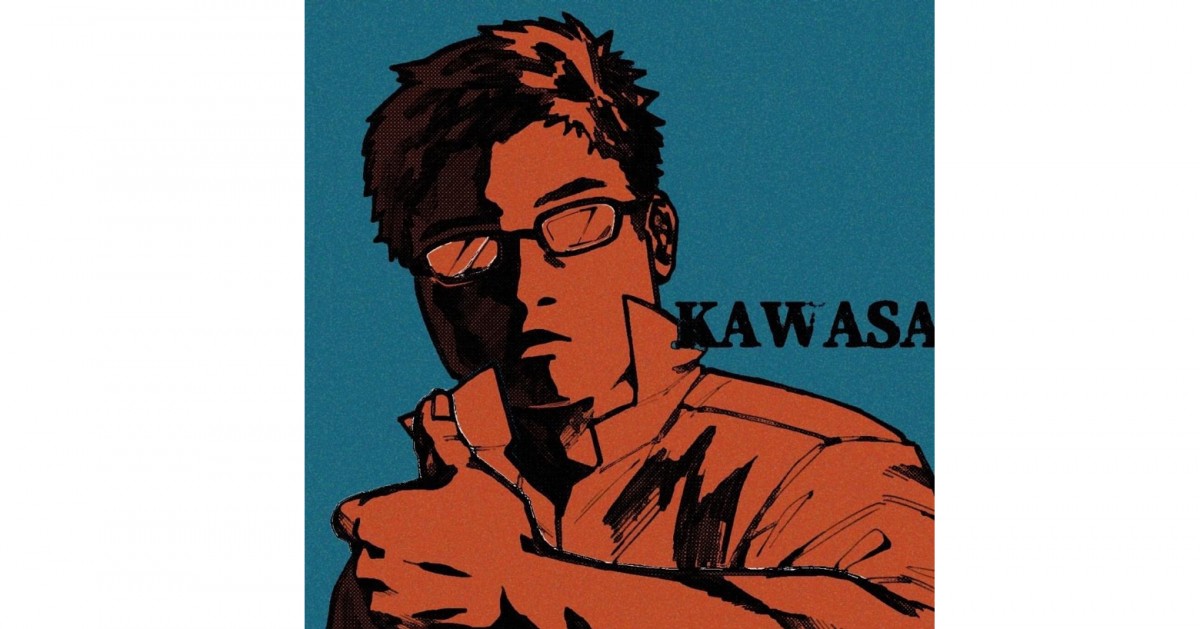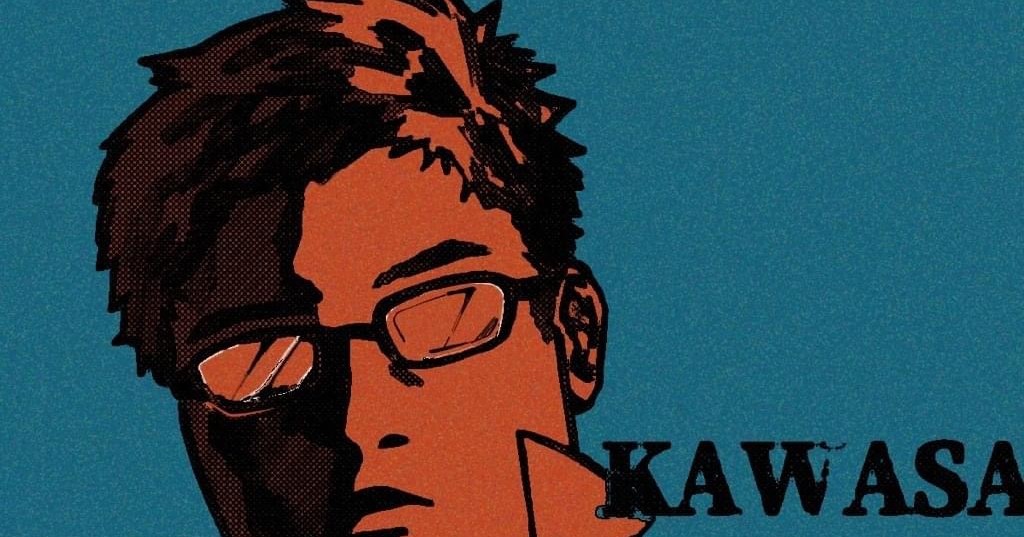世界ダウン症の日(World Down Syndrome Day)前編(理解編)
【まず「ダウン症」を知る】
ダウン症(Down syndrome)は、21番染色体が通常より1本多く存在することで生じる、先天的な染色体由来の状態です。人間は通常、22対の常染色体と1対の性染色体(合計46本)を持ちますが、ダウン症のある人は21番染色体が3本ある、つまり「トリソミー21」の状態にあります。
出生頻度はおおよそ800〜1,000人に1人とされ、若干の地域差はあるものの世界中どの人種や国でも一定の割合で生まれています。この21番染色体が1本多いというだけで、顔立ちや身体の特徴、筋緊張、発達のペースなどに特有の傾向が現れます。しかし、それは「障害」や「異常」である前に、その人一人ひとりの神経学的多様性の一つであり、一人ひとりの特性を表すものの一つと言えます。また一方で「ダウン症のある人の多くは豊かな感受性や人とのつながりを楽しむ力を持っている」と言われていますが、概ねその傾向にあるとしてもこれも結構ステレオタイプ的な表現であり、ダウン症である前に一人ひとりで異なる個別の見え方や実態があります。
知的障害を合併する事が多いですが、その程度も幅が極めて広い事がわかっています。名前や症状が独り歩きする以上に、「その人に合った環境や支援はダウン症の人々の生活を大きく拡大する事」を多くの方に知っていただきたいと思います。

【よくある疑問からダウン症を間違いの少ない形で理解する】
ダウン症になるのはなぜ?
ダウン症は、染色体の分離が偶然うまくいかず、21番染色体が1本多くなることによって起こります。21番染色体は人間の染色体の中で最も小さく、含まれる遺伝子の数も比較的少ないため、まるごと1本増えても生命の維持が可能である点から、完全トリソミーとして最も生存しやすい染色体異常の一つとされています。ただし、この21番染色体には脳神経系の発達に関わる重要な遺伝子も含まれており、その過剰な発現が認知や発達、感情調整などに影響を及ぼすと考えられています。これは、卵子や精子が作られるとき、あるいは受精の瞬間に起こる自然な確率的現象であり、誰にも予測やコントロールができません。
そもそも人間の始まりである受精卵の段階では、一定の割合で染色体の数や構造に誤りを持つケースが存在しています。受精卵の約50%に染色体異常があり、その多くは着床に至らず自然流産となることが知られています(Hassold & Hunt, 2001)。
こういった事実を踏まえるとこうした染色体構成の違いを「異常」や「疾患」と一括りにし、「異常な染色体を取り除くべきもの」と考えることは、本当に正しいと言えるのでしょうか(この論点は後半に続きます)?
さらに私たちが知っておくべき事実として、私たちは親から染色体を「コピー」して受け継ぐだけでなく、その過程で“組み換え”という遺伝子のシャッフルが起こります。これは多様性を生むための大切な仕組みですが、同時に、新たな遺伝的変異や疾患が“初発”として生まれる自然な背景でもあります。つまり、誰もが「何かを持って生まれてくる」存在であり、“完璧な設計図”のもとに生まれてくるわけではないのです。
ダウン症の発症要因として、母親の年齢が高くなるとその確率がやや上昇することは事実です。しかしこれは「年齢が原因」というより、年齢とともに“確率が少し上がる”にすぎず、若い母親からもダウン症のある子どもは生まれています(全体の確率分布的に多くは35歳以下のお母さんから生まれてくる、と言う報告もあります)。
さらに、研究によれば21トリソミーの約10%は父親側の減数分裂由来であることがわかっています(Lamb et al., 2005)。つまり、父母どちらか一方の親に責任があるという考え方は、科学的にも全く根拠がありません。
【ダウン症の人はみんな同じように21番染色体が1本多いの?】
実は、ダウン症といってもいくつかのタイプがあります。いずれも21番染色体の遺伝情報が過剰になっている点は共通ですが、その構造や出現の仕方が異なります。
標準トリソミー型:約95%。すべての細胞で21番染色体が3本になっている。
転座型:3〜4%。21番染色体が他の染色体、特に14番染色体や他の21番染色体に付着している。特定の染色体間で起こることが多く、遺伝的に均衡転座をもつ親から遺伝する場合もある。
モザイク型:1〜2%。一部の細胞のみがトリソミーの状態。
*タイプによって症状の現れ方や支援の必要性にも差が生じます。
【ダウン症の症状って?-何故いろいろな症状が起こるの?】
ダウン症のある人たちは、知的発達や身体の特徴、健康状態など、複数の側面に影響を及ぼす特性を持つことが知られています。つまり症状が多岐にわたるわけです。
これは、21番染色体まるごと1本分の遺伝子情報が余分に存在していることに由来します。たとえば、遺伝子変異が一軒の家の変化に例えられるとすれば、染色体異常は県単位の構造が丸ごと増えるような影響力を持ち、幅広い表現型の違いを生み出すからです(Strachan & Read, 2010)。
よく身体的特徴としては、顔の平坦な輪郭やつり上がった目、手掌線や指の特徴などが知られていますが、全ての人に当てはまるわけではなく、あくまで傾向であり個人差があります。
知的発達においても、軽度から重度まで幅があり、ゆっくりとした学習ペースで一人ひとりの発達のペースを持ちます。学習や記憶、言語発達、社会性の強みと困難のパターンも人によって異なります(Vicari, 2006; Karmiloff-Smith et al., 2022)。ただ、療育や個別の支援の有効性が高いことも明らかになっています。
さらに、ダウン症のある人々には健康面でのリスクも見られ、先天性心疾患や、消化器系の疾患(十二指腸閉鎖・狭窄など)、甲状腺機能低下症、眼の疾患、難聴なども比較的多く見られます。近年、医療の進歩により、これらの合併症に対する治療法も進歩しており、適切な治療と管理によって、ダウン症のある人々の予後は大きく改善し、平均寿命も延びています。現在では、平均寿命は60歳を超えるとも言われています(私が学生の頃はシビアな状況でした)。ただし、成人期にはアルツハイマー病を発症するリスクが高まる可能性も指摘されています。
このように、症状は多岐にわたり共通する傾向を持ちますが、その現れ方や程度は一人ひとり異なります。その人の「育ち」は単に21番染色体だけでなくその他の遺伝情報や環境との相互作用の中で決まるものですから。
感覚面においては、感覚過敏や感覚鈍麻など、特有の感覚特性を持つ人もいます。社会性においては、一般的に感受性が豊かで、人とのつながりを大切にする傾向があると言われています。しかし、これも前述した通り過度のステレオタイプ化は危険です。人づきあいが苦手なダウン症の方も少なくありません。ADHD特性やASD特性を持つダウン症の方もたくさんおられます。

「ダウン症」という言葉、特に「ダウン症だから」という言葉には「何もできない」といったイメージを結び付けがちです。これは適切ではありません。ダウン症を持つ人もそうではない人も皆、喜び、悩み、学び、愛し、社会とつながる力を持った人たちです。出来なことを探して制限を書けてしまうとより一層、その人の生活を狭めてしまう要因になりかねません。ましてや「問題のある染色体を取り除く」といった考え方は少なくとも私には理解できません。
【世界ダウン症の日によせて】
3月21日は、21番染色体が3本ある「トリソミー21」にちなんで制定された「世界ダウン症の日(World Down Syndrome Day)」です。この日は、ダウン症のある人たちとその家族の存在を社会が尊重し、多様性を祝福する日です。派手な靴下を左右バラバラに履く「ロックソックスキャンペーン」も、私たちが「多様性とは何か」に気づくための、ささやかなきっかけでもあります。ただ、そんなパフォーマンスがなくてもダウン症や障害のうむに「一人として同じ人間はいない」が当たり前になりますように。
後編では「21番染色体を取り除く」とした研究について➀研究内容②倫理的観点③我々が今後どう向き合うべきか考えていきたいと思います。
今回担当の川﨑のページです。https://kawasakiakihiro.theletter.jp/
【引用・参考文献】
Bull, M. J. (2011). Health supervision for children with Down syndrome. *Pediatrics, 128*(2), 393–406. [https://doi.org/10.1542/peds.2011-1605](https://doi.org/10.1542/peds.2011-1605)
Hassold, T., & Hunt, P. (2001). To err (meiotically) is human: The genesis of human aneuploidy. *Nature Reviews Genetics, 2*(4), 280–291. [https://doi.org/10.1038/35066065](https://doi.org/10.1038/35066065)
Karmiloff-Smith, A., Al-Janabi, T., D’Souza, D., D’Souza, H., & Thomas, M. S. C. (2022). Heterogeneity in cognitive and behavioral profiles among individuals with Down syndrome: A multidimensional scaling approach. *Scientific Reports, 12*, Article 5825. [https://doi.org/10.1038/s41598-022-05825-4](https://doi.org/10.1038/s41598-022-05825-4)
Lamb, N. E., Sherman, S. L., & Hassold, T. J. (2005). Effect of meiotic recombination on the production of aneuploid gametes in humans. *Cytogenetic and Genome Research, 111*(3–4), 250–255. [https://doi.org/10.1159/000086291](https://doi.org/10.1159/000086291)
Strachan, T., & Read, A. P. (2010). *Human molecular genetics* (4th ed.). Garland Science.
すでに登録済みの方は こちら