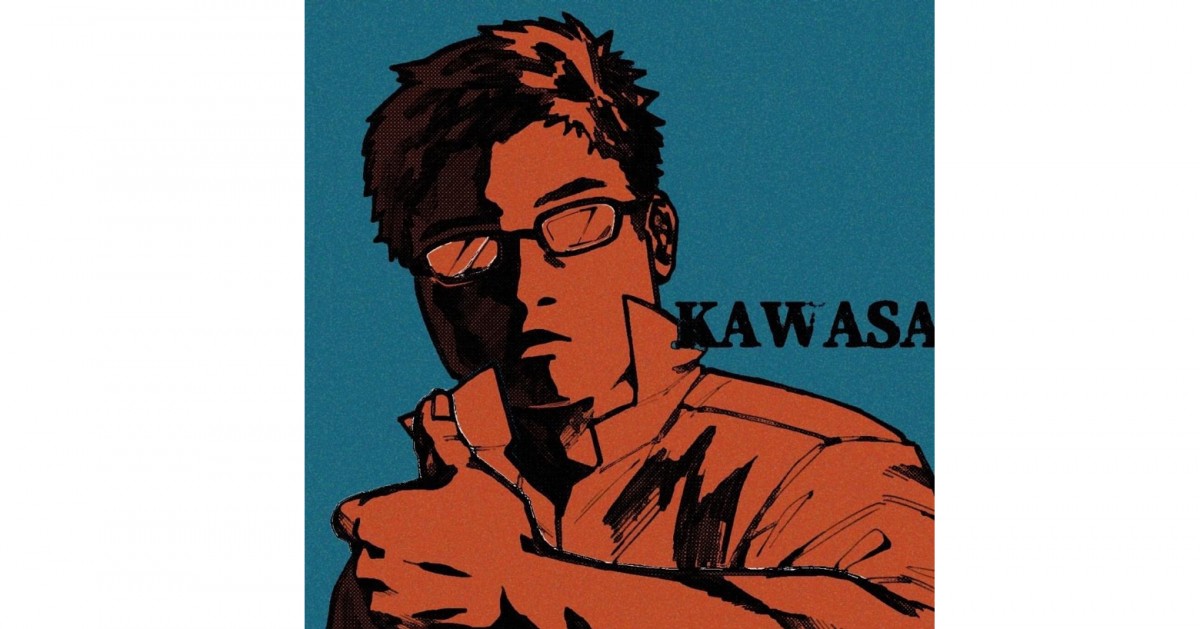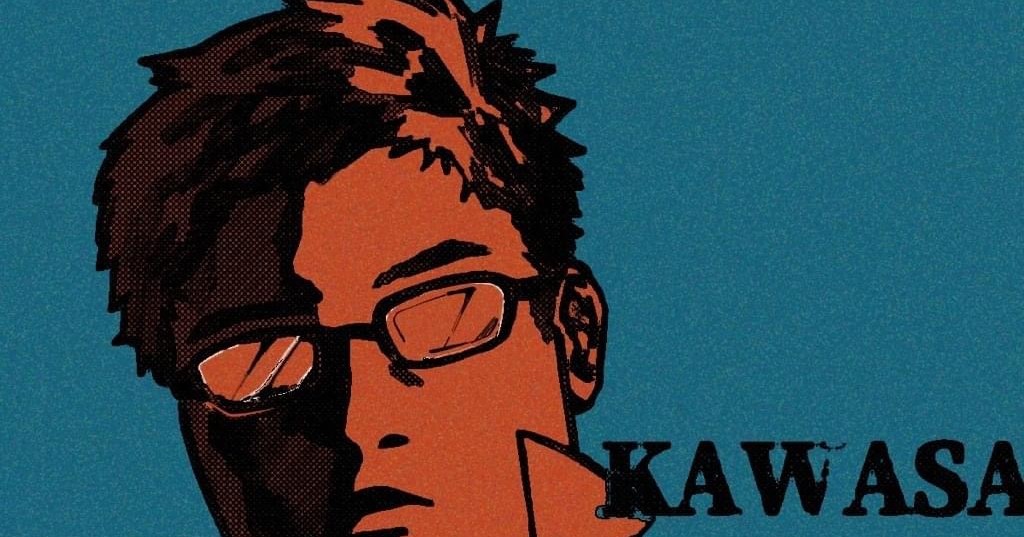「教育や医療における人の生活に役立つエビデンス」とは -レター始めるらしいぞ(自己紹介その➀川﨑聡大)-
第一回目は川﨑の担当回でございます。これからレターを配信する上で少しお目通しいただければ幸いです。
経歴:川﨑聡大(かわさきあきひろ):療育機関や大学病院勤務を経て研究職にうつりました。主にことばやコミュニケーションの発達とその支援について実践や研究を行っています。また発達障害の特性や特性によって生じるストレスに関する基礎研究を展開しています。持っている資格は公認心理師、言語聴覚士、特別支援教育士他。東北大学を経て2023年度より立命館大学産業社会学部教授(現職)*レターの内容は個人的見解であり所属と関係はございません。

「第三者に客観的に説明のできない名人芸に何の意味もない」
私が研究を始める(現場にいながら)きっかけがここにあります。支援をする相手の「出来る」「出来ない」双方必ず理由があり、その理由を精査する事でより良い支援が出来る(特別新教育も同様)。そのためには常に客観視できる開かれた「眼」を養っていく必要があります。このレターが私自身、そして皆様と一緒に学ぶきかっけとなるようにレター配信を開始するにあたって自己紹介をかねて3つの「きっかけ」、➀研究を始めるきっかけ、②研究者になったきっかけ、③支援介入の方向性を見直すきっかけ、についてお話しさせて下さい。
その1 研究を始めたきっかけから
率直に申し上げると「自分の臨床に自信が持てなかったから」が理由です。長らく療育センターや病院で療育や医療の現場に携わっていましたが、常々考えていたことが「今目の前で行っているセラピーが本当にその人の『幸せ』に役立っているのだろうか」といった事でした。大学院に進学しようと思ったのも同じ理由です。博士課程に在籍している時に大学病院の先生に「研究をやって有名になろう!」といわれて全くピンとこずに「いえ、(研究を通じてセラピーが)上手くなりたいです」と答えたことを覚えています。
一つの療法や手技、研究成果にこだわってしまうと、知らないうちに目的と手段が入れ替わり「それ」を守る事に汲々としてしまう。注目を集める成果であれば猶更その傾向が強くなります。結果として自分の視野に入らないものを否定し自分自身のアップデートも等閑になってしまいかねません。今行っているSNS等の発信も自分自身がそういったパラドックスに陥らないための手段(戒め)として機能させたいと考えています。
目的と手段が入れ替わる分岐点
一つの心理検査を作ったと仮定します。その検査に何らかの課題が示されたときに、時には批判的な意見も取り入れて改善しようとするか、示された見解に対して全力を挙げて否定し今ある検査(業績)を守ろうとするか、で大きくその人の在り方が変わります。最初は「こどもの理解や支援のために」という崇高な思いがあったはずです。その思いがあれば前者に至りますが、その後の過程で簡単に(知らないうちに)後者に堕ちる事もすくなくありません。発達支援の領域において取り上げる様々な事象の中で、この分岐点を皆様と一緒に(自戒をこめて)見極めたいと思います。
その2 研究者になったきっかけ
今でこそ、「大学の研究者」としてのイメージが強いかもしれません。実は現場出身でして、少し過去を振り返りたいと思います。遠い昔(自分ではまだ若手のつもりですが)大学では特別支援教育を勉強していました。実際に発達障害や知的障害をもつこどもの発達支援を志し、臨床が充実した別の大学院修士課程に進学し、その後現場に出て病院臨床(成人・神経心理)から療育センターでの小児の療育を経て、岡山大学医学部博士課程に在籍しつつ岡山大病院でこどもから大人までの臨床に従事していました。大学病院時代から研究を本格的にスタートさせていますが、それまで勤務させていた職場がしっかりと自己研鑽に理解があった事、常に支援全般において「(今やっていることは)本当にこの人の数年後の『幸せ』に役立つのか?」という視点で考える姿勢が徹底されていたことが研究に向かう基盤にありました。そして最初の表題「第三者に般化できない名人芸に何の意味もない」に戻るわけです。「名人芸とされているものを徹底的に科学し(その結果を)世に出していきたい」と考えたのが研究者になったきっかけです。
エビデンスは日夜変化する
教育・医療・福祉の領域はまだまだエビデンスが十分ではないために一部の経験の過剰般化や非科学的な精神論がまかり通る事が少なくありません。また「エビデンス」とされたものもどんどん書き換わっていきます。難聴の原因に関する専門書の記述も20年前と今では大きく異なりますし、デュシャンヌ型筋ジストロフィーに対する遺伝子治療のここ数年での目覚ましい進展は病弱児の心理生理病理の教科書の多くに書き換えを迫る事になります。こういった変化を知る、対応できる、コンテンツにこのレターを皆さんと一緒に育てていきたいと思います。
その3 支援介入の方向性を見直すきっかけ
「(スクリーニング検査で)点数が下回っていたから@@障害だ(だから介入が必要だ)」
療育や教育の現場でよくあるシチュエーションだと思います。もちろんこれはすべて間違いというわけではありませんが違和感を持ってもらいたい。ただ特に機能に直接介入する際には、「誰のための・何のための」介入か考えておく必要があると思います。介入は発達障害の特性を治すためでも、変形発達に近づけていくためでもありません、その人の望むよりよい生活のために出来る事を一つでも多く増やしていくことにあり、その結果が多様な特性に左右されない安心安全な生活につながるわけです
私も読み書きの困難さがあるこどもたちに対して直接読み書きの指導を行っています。苦手なことを敢えてやるわけです。「君はほかの子に比べてひらがなやカタカナが読めない書けないから訓練しているんだよ」なんて絶対に私は言いません。学力に対して学習意欲は重要な要因ですが、いわゆる継続的な努力以上に学習に対する不安が学力に対して大きな影響を持ちます(先行研究)。いくら本人が頑張っても別のところで不安を煽ってしまっては元も子もないわけです。まず介入によってどんないいことがあるのか本人と共有します。一番大事な事(介入の方向性・目標)は読み書きの介入を通じて自分の「学習の様式」に前向きに気づいたり、少しでもできるイメージを持って貰ったり、学習に伴う不安を少しでも減らして学習を楽しくすることが目的です。学習意欲に関しては改めてレターで書かせていただこうと思っています。

次回に向けて
これから心理学や教育学、発達障害の領域を中心に医療や福祉に関わるトピックスをどんどん取り上げていきたいと考えています。注目を当てていきたい論文や本、さまざまな取り組みについても積極的に取り上げて説明をしていこうと思っています。積極的に皆さまからもリクエストいただけると幸いです。
次回(川崎の回)は「五歳児健診」を取り上げていきたいと思います。本来の目的や課題を生理するだけでなく、それぞれの地域にあった提案も考えていきたいと思っています。
~3人の井戸端会議~
荻布「川崎先生のいう『名人芸』っていったいどういうものをさしているの?」
川崎「先生には『えええ!』と驚かれてしまうかもしれないけど、一昔前には教育や療育の実践に携わっている人で指導のきっかけや改善のメカニズムを客観的に相手に話す文化を持ち合わせない人が一定数いたんですよ。さらにすごい!と持ち上げられると、本来の主旨から切り離されて方法論が独り歩きすることも。10人のうち7人に上手くいってると3人の何故?が見過ごされてさらに7人の上手くいった背景も掘り下げなくなる。『単なる名人芸』はちょっとスパイスを利かせた例えです。」
奥村「先生の言ってることは全く共感できる。たださ、現場の人たち全員が研究をやるわけでもないよね。そこどうしたらいい?」
川﨑「おっしゃる通りだと思います。例えば指導の効果に関する素晴らしい研究も目の前の事象を100%説明できるものではそもそもないですから。大事なことは研究をやる事ではなく、『自分のやってることは間違ってるかもしれない』『もっといい方法があるかもしれない』とその人の立場で出来る事を常に考える姿勢がだと思っています。現場か否かに関わらず人に関わる職業に就くうえでですが」
様々な情報にはエビデンス(確証)のレベルがあり、それを見極める力の一助にこのレターを役立てていただければと思います。また、エビデンスは結論ありきで自分の主旨を立証するために恣意的に利用しない事も重要な点だと思っています。
次回は『「見る」はどれだけ「学び」に関係する?―眼鏡店から始まった私の探求(自己紹介その②奥村智人)』です。おたのしみに。
すでに登録済みの方は こちら