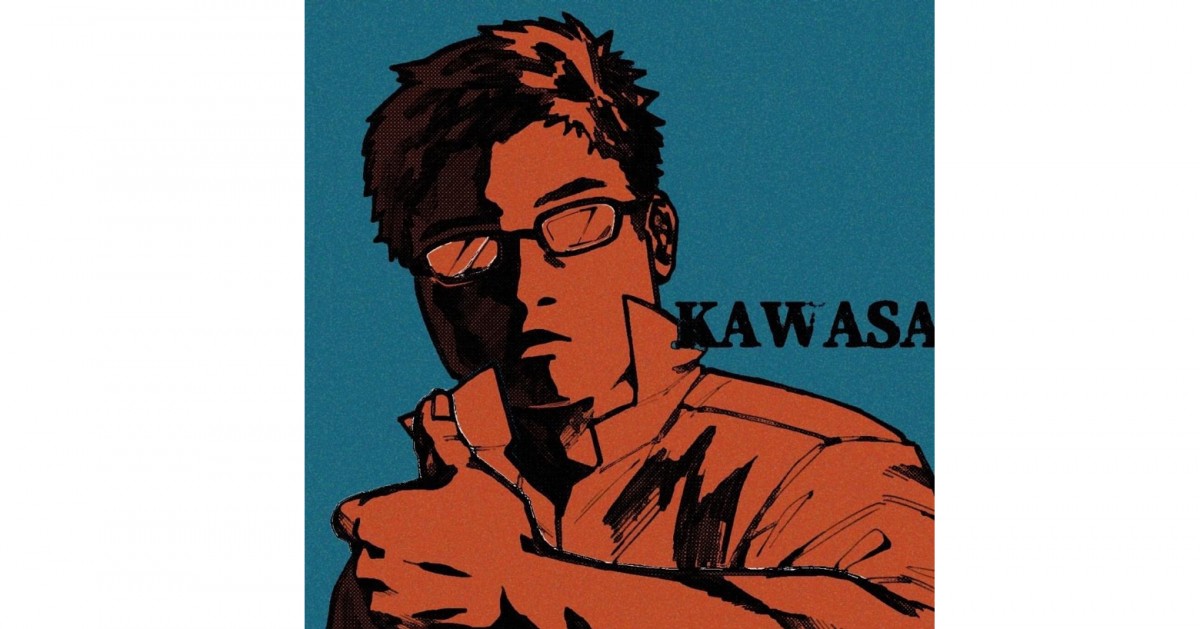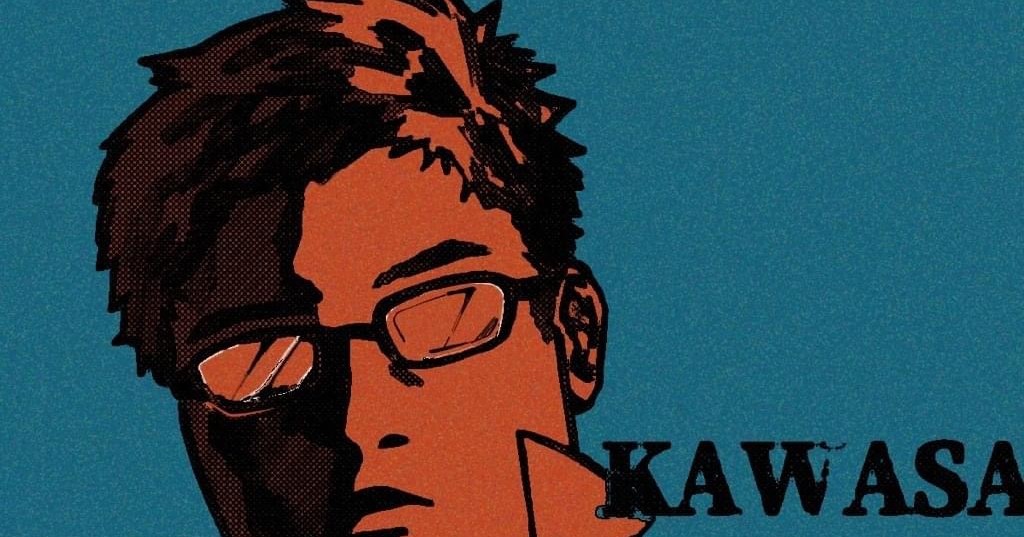“障害かどうか” は支援を始めるためにそれほど重要なことなのか? (自己紹介その③荻布優子)
経歴:荻布優子(おぎのゆうこ):療育センターに心理士として勤務(発達期の発達障害・知的障害・肢体不自由等のアセスメントと支援、保護者支援、学校園とのコンサルなど)していましたが、2019年から大学で教員養成をしています。2024年4月より長崎大学教育学部准教授、専門は読み書きに苦手さのある子どもの指導と支援…とお話することが多いです。Letterで綴ることは個人的見解であり所属とは一切関係ございません。

Letterを始めるらしいです…
荻布優子(おぎのゆうこ)です。ちょっと苗字が読みにくいです。長崎大学教育学部で特別支援学校の先生を目指す学生さんたちと日々一緒に学んでいます。公認心理師、臨床発達心理士、特別支援教育士SVの資格を持っています。療育センターで心理士として働いたり、スクールカウンセラーをしてきた経験があります。
業界的にはまだまだ若手のわたしにはこんな機会は滅多にありませんので、これまでの経験を振り返りながら、わたしが目の前の「あなた」と接するときに大切にしたいと心にとめていることを書いてみます。
“障害かどうか” は支援を始めるためにそれほど重要なことなのか?
大学院修士課程修了後、横浜市にある療育センターで知的障害・肢体不自由・発達障害などの幼児のアセスメントや初期療育、幼稚園・保育園とのコンサルテーションの仕事をしていました。わたしは小学生くらいのころから、特別支援学校の先生になることを夢見ていました。そんな私が進路変更したのは、大学や大学院で学ぶうちに発達障害児への支援は「早期発見・早期介入」が重要であり、特性を有する子どもたちをできるだけ早いタイミングで支援したい、就学して二次障害を引き起こす前に介入したい、と考えるようになったからです。幅広い障害種や様々な家庭状況にある子ども達とそのご家族の支援に携わった経験は、私の凝り固まっていた頭をゴリゴリとほぐし、狭まっていた視野をこじ開けてくれました。
医療や福祉の現場は、制度設計上ある程度は仕方がないこととはいえ、診断(障害があること)を前提として支援・サービスが進んでいきます。早期介入が重要視されるのは障害に起因する二次的な困難を最小に抑えていきたいからなのに、生活上の困難さが大きくならないと支援をはじめられません。医療には医療、福祉には福祉、それぞれ大事な譲ってはいけない守備範囲があります。でも生活の困難さがそれほど大きくなくても、診断がなくても、欲をいえば予防的に支援を開始できる場所はないだろうか…と、うんうん唸って考えた結果、それは個人の教育的ニーズが生じた時点で支援を始められる教育の現場なのではないか、と思い至りました。そして今、私は、教育学部で特別支援教育を教えています。
“知って、納得して、自分で決める” を支えたい
大学教員となってあっという間に6年が過ぎました。大学に勤めたからといって講義や研究ばかりというわけではなく、小学校・中学校・高校・特別支援学校…すべての学校種でスクールカウンセラー(SC)をしてきました。療育センターでも、SCでも、大学で学生を指導するときも、わたしが目の前の「あなた」とかかわるときに大切にしていることは、“知って、納得して、自分で決める”という姿をサポートしていきたいということです。「あなた」が困っているご本人のときも、保護者の方のときも、先生や支援者のときも、私はいつもこのように考えています。
わたしたちの人生は、ちょっとしたことでも、人生の分岐点でも、たくさんの選択を迫られます。その時々に納得のいく判断・決断をしようと思うと、間違いの少ない情報が必要不可欠です。「どこかの誰かがおススメだといったから」という理由で選択を重ねてくことは、「あなた」の本当の幸せにつながるのでしょうか。ここでいう情報には、発達に関する情報、障害特性に関する情報、得られる支援の情報、社会資源の情報、あるいは自分自身の認知の特徴に関する情報、我が子の発達の様相に関する情報、など色々を含んでいます。
この3人でLetterを始めるにあたって「必要な情報、間違いが少ない情報、客観性の高い情報を届けたい」という思いが根底にあります。単なる研究者の立場だけではなく、実際に医療の心理職や学校現場でSCを経験してきた立場だからこそ見えてくる情報を共有していきたいと思っています。
根拠に基づいて “寄り添う” ということ
数は多くありませんが、学生さんと一緒に学校生活に困り感のある子どもたちの個別支援も行っています。ここでは“根拠に基づいて子どもたちに寄り添う”姿勢をもった支援者を一人でも増やしたい、子ども達の困り感や不全感を少しでも減らして心穏やかに過ごしていけるように、と思いながら取り組んでいます。
本当に子どもに寄り添おうと思うなら「愛情」や「熱意」だけでは十分とはいえません。ただ気持ちに共感して寄り添うだけでは、実際の生活の困りごとは解決してはいきません。根拠に基づいて、具体的なノウハウを持って、生活の具体的な場面に介入していく必要があります。そこにはやはり大前提として「必要な情報、間違いが少ない情報、客観性の高い情報」が必要だと思います。情報!情報!と多少頭でっかちに思われたとしても、正しい知識や情報の力は馬鹿にはできません。

これからLetterでやってみたいこと
発達障害や子どもの育ちに関する情報発信はもちろんのこと、ふたりのオジサン先生(だれがオジサンやねん!と関西のオジサン川崎&奥村からツッコミ)と比べると経験は少ないかもしれませんが、SCなど学校現場での経験を踏まえてより読者の方々に近い視点から、素朴な感想や疑問をお二人の先生に投げかけていきたいと思います。
またわたしは本を読んだり、映画をみたり、ドラマを見たり…といったことが昔から大好きです。発達障害がこういった創作物のなかに取り上げられることも増えてきました。流行りに乗っかりながら(笑)、発達障害が登場する書籍やドラマについて解説というか…わたしなりに思い感じたことを、関連する研究知見も交えながら共有していけたらいいなと思っています。
~3人の井戸端会議~
奥村:荻布先生の一番いいところっていうか僕たちオジサン2人にないところは、ガチ療育の現場から研究者になってからの日が浅い、つまり現場の感覚に近いっていうところだと思うんですね。その上で、今、学生や周りの人から「早期発見・早期介入っていうのは本当に意味があるんでしょうか?」って質問を受けたとしたら、どう回答します?
荻布:意味があるかないかといえば意味はあるといえるし、「意味があるものにしないといけない」と答えたいです。早期発見・早期介入は「診断すること」だけを指すのではなくて、「毎日の生活が安心して送れるように早い段階から介入していく」ということかなと思うんですね。早期療育に携わる人の心構えと、診断に関わる人の心構えが同じであってはいけない…立場が違えばとやることも違って当然・でも目指すゴールは同じ、ということを専門家が各々で自覚して、関わっていかないと本当の効果は出ないと思います。
川崎:根拠に基づいて寄り添うことってとっても僕も大事だと思う。先生は1人の子どもに支援をするときに直接その子どもの支援だけじゃなくって、保護者や先生に対してもアプローチをすると思うんだけれども、それぞれの立場で1人の子どもに対して寄り添うときの違いを教えてください
荻布:どの立場でも共通するのは、それぞれの立場で子どもの安心安全を守るということです。保護者・養育者は家庭での子どもの安心安全を守ること、教員は学校生活での安心安全を守ること、心理士というかSCは家も学校も含めた日常生活全般の中で安心安全が守られているかをモニターして、それが脅かされるような状態であればコンサルテーションするし…っているのが最低限の役割になると思います。大人が具体的に介入できるそれぞれの場面での役割分担は大事と思いますね。もちろん一人一人のおかれている環境とか課題によっても変わってくるので一概には言えないけど、養育者は養育者であって学校の先生でも支援者でもないし、学校の先生はあくまでも教育を行う専門家であって心理士ではないし…。協働していくことは大事だけども、それぞれの役割を超えてしまうことを避けられるようにというところは意識して、保護者や先生へのアプローチを考えています。
奥村:先生は演劇も見るし、本もよく読みますよね。最近印象に残ったドラマ何かあります?
荻布:「宙わたる教室」でしょうか。定時制高校が舞台のドラマで、連立方程式とか複雑な計算も暗算でできるのに、文章問題には一切手を付けない生徒が出てきます。それを主人公の先生が不思議に思い、文章問題を先生が読み上げたら聞いて理解してスルッと正解できるんです。運転免許を取りたいけどもどうしても学科試験に落ちてしまう、ずっと勉強ができない、勉強ができるようになりたいと思って定時制に入学したけれどうまくいかず、1年通って「これが自分の限界」と思い退学届けを書いてきます(それも間違って書いている)。
先生が「専門じゃないけど、たぶんディスレクシアだと思う」といきなり生徒に伝えたシーンはヒヤッとしましたが(現実でこんなことを言い出すのはナンセンスと思いますが…)、「文章問題は疲れるんだ、見ているだけで吐き気がしてくる。全然意味が入ってこねぇ。」という生徒の今の困りを吐露するシーン、子どものころに「もっと頑張れ」「辛抱が足りないんじゃないか」「みんなと同じになれないよ」と大人から言われている回想シーン、先生が「ディスレクシアは自覚がないまま(本人も障害だと気が付かないまま)大人になるケースがある」「ずっとしんどい階段を上り続けているようなものらしい」と解説するシーン、など1話のなかにディスレクシアの理解されにくいけども、もっともっと理解が広まってほしいと思っている部分がぎゅぎゅっと詰まっていました。
次回から本格配信を始めます。川崎を中心に「5歳児検診」を取り上げる予定です。おたのしみに。
すでに登録済みの方は こちら